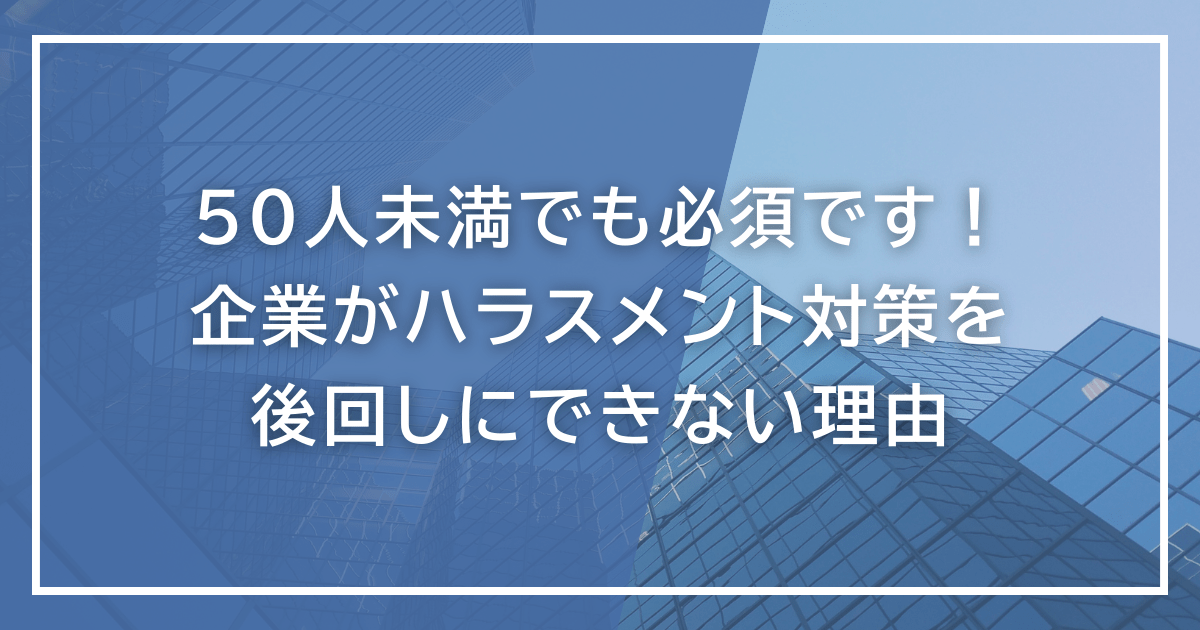「うちは小さい会社だから大丈夫」——そう思っていませんか?
実は、パワハラやセクハラの相談件数は、必ずしも大企業だけの問題ではありません。
2022年の法改正以降、企業規模に関わらず「防止体制の整備」が強く求められています。
本記事では、コストを抑えつつ実効性を高める方法も交えて、「50人未満でもやるべき理由」をわかりやすく解説します。
- 小規模企業ほどトラブルが隠れやすく、深刻化しやすい
- 外部ツール・助成金を活用すれば、低コストで実効性ある研修が可能
- 形式的対応ではなく、現場で機能する仕組みを設計することが重要
ハラスメント対策は「50人未満でも義務」って本当?
正直、このテーマはちょっと胃がキュッとしますよね。
「うちは20人もいないのに、そんな大げさなこと必要?」——そう思うのも自然な反応です。
でも、答えはシンプル。必要です。
パワハラ・セクハラ・マタハラ対策は、2020〜2022年にかけてすでに全企業で義務化。
さらに2025年6月には法律が一歩進み、カスタマーハラスメント(カスハラ)と就活セクハラへの対応も「努力目標」ではなく「やるべきこと」になりました(最短で2026年施行予定)。
規模は関係なし。
「努力義務じゃなかった?」という声もよく聞きます。
でも、努力義務は「やったほうが良い」レベル。
今は「やらないといけない」段階です。
つまり、「まずは直して」「次は正式に注意」「それでもダメなら社名が出る」…ブランドや採用に響くのは言うまでもありません。
ピンと来ないなら、現場の風景を思い浮かべてみてください。
たとえば従業員18名の小売店。
クレーム対応の基準がなく、店長さんが毎晩ぐったり。
放置していたら、ある日お客さま対応の録音がSNSに出て、休日も電話が鳴り止まなかった——なんてケースもあります。
一方、従業員30名の製造業は早めに動きました。
「言っていいこと・ダメなこと」をカード化し、産業保健総合支援センターや厚生労働省「あかるい職場応援団」の無料資料で基礎を学び、匿名で相談できる外部窓口を契約。
半年後、「一人で抱え込む」場面が明らかに減ったそうです。
数字より、「現場が少し呼吸しやすくなった」という実感が大事なんですよね。
就活の場面も要注意です。
面接で「結婚の予定は?」「実家はどこ?」——つい口にしてしまいがちな質問が就活セクハラに該当します。
今は学生も企業もSNSですぐつながり、スクショが一瞬で広がります。
この「さじ加減」が問われる時代です。
「でも何から?」という戸惑いには、こう返します。
防災訓練と同じです。
火が出てから消火器を探すのは遅い。
まず「避難経路」=方針と就業規則を整え、次に「消火器の使い方」=社員・管理職教育を押さえる。
そして「119番の窓口」=相談ルートを周知する。
ここまでが最低限のセットです。
教材は有料じゃなくてもOK。
厚生労働省「あかるい職場応援団」や「こころの耳」は無料で使えますし、民間企業による社外相談窓口サービスの導入も現実的です。
そして忘れないでほしいのは、対策は「社員のため」だけじゃなく、経営者さま自身を守るためでもあるということ。
小さな会社ほど、一人の不調や炎上が直撃します。
だからこそ、小さく始めて、早く回すのが正解。
- 来週は社内掲示に「ハラスメント方針」を貼る
- 再来週は昼休みに「あかるい職場応援団」の動画を流す
- 月末は相談窓口の連絡先をカードにして配る
たった三歩で、社内の空気は変わります。
中小企業が直面する「リアルな悩み」とは?
「ハラスメント対策は必要だと分かっているけれど、正直どこから手を付ければいいのか…」
この声、ここ数か月だけでも経営者さまや人事担当の方から何度も耳にしました。
特に中小企業では、日々の業務に追われて「後回し」になりがちです。
ですが、その油断が思わぬ落とし穴につながるケースも少なくありません。
「何から始めればいいのか分からない」
ある町工場の社長さんが、「相談窓口? 規程整備? 研修? 頭が痛いよ」とぼやいていました。
必要なことは分かっていても、優先順位が見えず足踏み状態――そんな企業は意外と多いのです。
「コストや工数が負担」
研修やコンサルティングと聞くと、「うちはそんな余裕がない」と身構える方もいますよね。
私も以前、地方の飲食チェーンのオーナーさんから「売上が厳しいのに、研修なんて無理だ」と本音を聞きました。
しかし、「形だけ」の対応はかえって高くつきます。
ある会社はマニュアルだけ用意して安心していたところ、トラブルがSNSで拡散。
「従業員が少ないから形式だけで済ませたい」
「うちは少人数だから問題なんて起きないよ」という声もよく聞きます。
でも、人間関係が近すぎる職場ほど、不満やトラブルが表に出にくいんです。
「お客さまクレーム=カスハラ対応の線引きが不明確」
2025年改正法で義務化されるカスタマーハラスメント対策。
これが一番難しいという声も多いです。
「理不尽な要求」と「正当なクレーム」の境目は曖昧ですよね。
先日、サービス業の現場で働く方から「毎日胃が痛い」と打ち明けられました。
よくある誤解や不安
「研修は大企業向けでしょ?」
実は、厚労省のサイトには無料で使える中小企業向け教材や動画が揃っています。
「相談窓口なんて不要じゃない?」
2022年からパワハラ防止は全企業に義務化されました。
規模に関係なく、対応を怠れば行政指導の対象です。
失敗事例から学ぶ
ある小売業では、相談窓口を「形だけ」作ったせいで、被害を受けた社員さんが声を上げられず、結局SNSで告発され炎上しました。
別の製造業では、社内でハラスメントが軽く見られ、優秀な人材が次々に退職。
採用難の今、それは致命的なダメージでした。
共通するのは、「うちは小さいから大丈夫」「お金をかけたくない」という油断や短期的な発想です。
ここまでで、中小企業が抱えるリアルな悩みや誤解、そして実際に起きた失敗例を見てきました。
では、限られたリソースの中でどうすれば効率よく、しかも実効性のある対策が取れるのか?
次は、その「現実的な解決策」を一緒に考えていきましょう。
義務化に備えて、今できる3つのステップ
2025年6月に決まりました。
いよいよハラスメント対策の義務が広がります。
パワハラ・セクハラ・マタハラだけじゃなく、カスタマーハラスメント(カスハラ)や就活セクハラまで対応必須。
正直「うちは中小企業だから無理…」とため息をつきたくなる話です。
でも、実は全部を一気にやる必要はありません。
3つのステップで、無理なく進めることができます。
1.まずは社内ルールを「形」にする
最初に着手すべきは、ハラスメント防止の方針や就業規則の整備です。
「紙に書くだけで意味ある?」と思うかもしれません。
たとえば、ある製造業の小規模企業では、社内掲示板に防止方針を貼っただけで「牽制効果」が出ました。
上司が部下に声をかける時、「あ、掲示してあったな」と意識するようになったそうです。
2.次は教育。30分の動画でも十分動き出せる
ルールがあっても、現場が知らなければ意味がありません。
特に管理職は「どこまで注意していいのか」迷いがちです。
全社員向けには基礎知識を、管理職向けには実際の判断訓練を。
たとえば、厚生労働省「あかるい職場応援団」の研修動画。
30分程度で基礎を網羅でき、しかも無料。
あるIT企業では朝ミーティング時に視聴し、その場でちょっとしたディスカッションをしただけで、職場の雰囲気が変わりました。
3.相談窓口は「外に置く」のもアリ
「専任担当を置く余裕がない」——そんな声はよく聞きます。
でも、外部相談サービスを使えばシンプルに解決できます。
外部相談サービスを導入した小売業の社長さんは「社員が直接相談しやすくなり、問題が表に出るようになった」と話していました。
カスハラ・就活セクハラの備えも忘れずに
最近はSNSで接客の様子が簡単に拡散されます。
顧客からの過剰な要求や暴言にどう対応するか——その場で判断できる基準が必要です。
実際に飲食チェーンでは、「ここから先は店長に交代する」というラインをマニュアル化。
現場スタッフの負担が大幅に減ったそうです。
就活セクハラも見落としがちです。
面接で「結婚の予定は?」なんて何気なく聞いた質問がSNSに載れば、一瞬で評判が落ちます。
メールでの絵文字乱用や、馴れ馴れしい言葉遣いも要注意です。
一歩目は、シンプルに
義務化対策は「①ルール整備」「②教育」「③相談窓口」の3ステップで十分。
そのうえで、カスハラや就活セクハラの具体策を加えると、企業の信頼度はぐっと上がります。
大切なのは「とりあえず形だけでも作る」こと。
- 来週は防止方針を掲示する
- 再来週は30分の研修動画を流す
- 月末は外部相談窓口の案内を配る
このくらいの小さな動きでも、社内の空気は変わります。
コストを抑えても「効く」ハラスメント対策はできる
「ハラスメント防止なんて大企業の話でしょ。うちは規模が小さいし、費用もないし…」
中小企業の経営者さまや人事担当者さまから、こんな声をよく耳にします。
実は私も、以前クライアントから同じ相談を受けたことがありました。
その会社は、たった20人の社員で回していたのですが、ある時パワハラの噂が広がり、優秀な若手が2人も辞めてしまったんです。
「費用を理由に後回しにすると、結局もっと高くつく」
この言葉を、私は何度も実感しました。
離職、訴訟、SNSでの炎上…今は形式的な対応ではまったく通用しません。
でも実は、そこまでお金をかけなくても実効性のある仕組みは作れます。
たとえば、オンライン研修や外部相談窓口の活用。
「日本ハラスメントカウンセラー協会」のeラーニングや「パソナ」のオンライン研修は、小規模企業でも無理なく導入できて、社員が自分のペースで学べるのが魅力です。
ライブ形式を組み合わせれば、質問もその場で解決できるので、理解が深まります。
厚生労働省の「人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)」や、各自治体が独自に用意している補助制度を使えば、研修費用の一部をまかなえます。
社会保険労務士や商工会議所に相談すれば、最新情報が手に入りますよ。
そして、「やった感」では終わらせない研修設計が大切です。
ただ動画を流すだけではなく、ケーススタディやロールプレイを入れて、「もし現場で起きたらどう動くか」を具体化しましょう。
管理職なら「相談を受けた時の初動対応」、社員なら「迷ったときの報告ルート」など、役割ごとに実践的な内容を学ぶと効果が段違いです。
たとえば民間企業などの外部相談窓口を導入すれば、専任担当がいなくても迅速に対応できます。
ただし、最終判断は社内で下す必要があります。
外部サービスと社内対応のバランスを明確にしておくと安心です。
結局のところ――
低コストで実効性の高い体制を作るには、「外部サービス・助成金・オンライン研修」をフル活用しつつ、現場で本当に機能する仕組みを整えること。
社員が安心して声を上げられる職場は、それだけで人が辞めにくくなり、企業の信頼も高まります。
事後対応と予防研修のコスト比較(概算)
| 項目 | 事後対応になった場合 | 予防研修しておく場合 |
|---|---|---|
| 訴訟・和解費用 | 100万円~500万円 | ― |
| 離職・採用コスト | 50万円~100万円 | ― |
| 社員研修費用 | ― | 1人あたり1万~3万円 |
| 社会的信用失墜 | 高い | ほぼなし |
低コストで実施可能な研修・対策パターン
| 対策方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| eラーニング研修 | 時間・場所を選ばず実施可能 | 受講状況の確認が必要 |
| Web会議型ライブ研修 | リアルタイム質疑応答が可能 | 日程調整が必要 |
| 外部相談窓口サービス | 専門家対応で迅速 | 社内での判断体制も必要 |
| 助成金の活用 | 費用の一部を国・自治体が負担 | 申請手続きの確認が必要 |
まとめ
小規模だからといってハラスメント対策を後回しにすると、トラブル発生時の対応コストは一気に膨らみます。
オンライン研修や外部相談窓口、助成金制度を賢く組み合わせれば、低コストで現場に根付く仕組みを作ることが可能です。
形式的な「やった感」ではなく、社員が安心して声を上げられる体制づくりが、企業の信頼と定着率を守る近道です。